
ジャズ・ハーモニーを理解するために
改訂版 ヒアリング・ザ・チェンジ
定価3,564円(本体 3,300円+税)
著 : Jerry Coker (ジェリー・コーカー) / Bob Knapp (ボブ・ナップ) / Larry Vincent (ラリー・ヴィンセント)
翻訳 : 小幡 英司(翻訳監修:井上 智)
監修 : 佐藤 研司
コード進行を理解して 一瞬で耳コピする秘訣を身に付ける
-


イージー・ジャズ・コンセプション クラリネット
著:Jim Snidero (ジム・スナイデロ)
-
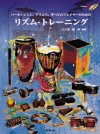

リズム・トレーニング
著:大久保 宙
-


【日本語翻訳解説書付属】The Jazz Singer’s Handbook
著:Michele Weir(ミシェル・ウィアー)
-


12キーで練習するジャズ・ライン
著:Steve Rawlins (スティーブ・ローリンズ)
-


イージー・ジャズ・コンセプション テナー/ソプラノ・サックス
著:Jim Snidero (ジム・スナイデロ)










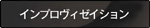
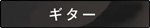
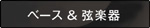
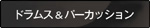
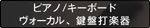
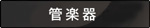
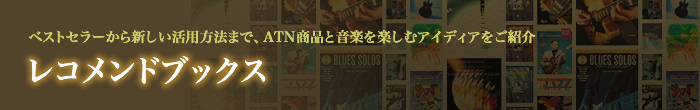
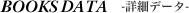
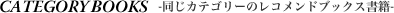
“ヒアリング・ザ・チェンジ”というタイトルだけ見ると、内容は分かりづらい・・・この本、タイトルで損してます。しかも、表紙も地味ときたもんだ(爆)でもね、外見だけで判断してちゃいけません!この本、ニューヨークやボストンのバークリーなんかの学生たちに使われているだけのことはあるんです。
“チェンジを聴く”ってことですが、このチェンジとは楽曲のコード・チェンジ(ハーモニー・パート)のことですね。じゃ、コード・チェンジを聴いて何をするのかというと、“その曲がたとえ知らない曲でも、耳で聴くだけで曲のハーモニーを即座に把握する” というスキル、すなわち音楽家としての必須条件である“音楽的な耳”を鍛えたいわけです。
では、“耳で聴くだけで曲のハーモニーを即座に把握する”というスキルを進化させることによって、実際にどんないいことがあるのかというと、
● 自在にメロディやハーモニーをプレイできる
● 自在にインプロヴァイズできる
● 自在にアレンジできる
● 自在に作曲できる
などなど(他にもありますが・・・)、ミュージシャンとしての可能性が一気に広がります!
そりゃね、なんでも自在にできりゃ言うことありませんけど、そうそう簡単にいくわけないと思うでしょ!?
確かに簡単じゃないかもしれないけど、非効率的な方法(膨大な数のスタンダードなどを片っ端から聴いて丸暗記するとかね・・・)に比べるとはるかに効率的なメソッドがあるんです!しかも、基礎的なハーモニック・セオリーの知識があればマスターできる確率はかなり高い。まさにそのような効率的&独創的なアイデアを提示してるのがこの本です!
簡単に説明すると、次の通り。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
そもそも曲なんてものは星の数ほどあるんだから、
そのコード・チェンジを全部丸暗記なんてナンセンス
↓
で、曲の構造をよくよく見れば、いくつかのハーモニック・パターン
(もしくはそのバリエーション)の組み合わせってことが多々ある
↓
ならば、“よくあるハーモニック・パターン”と
それらの組み合わせ方”を知った方が実用的なスキルとなる
↓
結果的に、膨大な量の曲を、ソング・フォームとコード・チェンジの
両面から効率よく整理して把握できる
↓
そこまで整理したら、そのサウンドを耳に覚えさせれば
いずれ聴くだけでもそれが何なのか判断できるようになる
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ってことです!
具体的に、よくあるハーモニック・パターンとは、
● Ⅱ-Ⅴ-Ⅰプログレッションとそのバリエーション
● Ⅱ-Ⅴ-Ⅰを使った経過的転調
● 一般的な転調
● 曲の導入部分のハーモニー
● よくあるブリッジのパターン
● 規則的(シンメトリカル)なコード・プログレッション
● 最近使われるようになったコンテンポラリー系パターン
● その他モロモロ
なんかを指します。これらを組み合わせたら・・・大抵のスタンダード・チューンはフォローできちゃいそうでしょ!
もちろん、パターンごとの解説と、それを実際に含む曲(スタンダード・チューンの曲名)が、その都度たくさん提示されます。ということは、似たようなハーモニック・パターンを含む曲を効率的に整理できるということですね。
そしてこの本の最大の持ち味なんですが、これらをハーモニック・セオリー的に解説するのではなく、あくまでも耳で聴いて判断できるように仕向けてるところなんです。
実際に演奏するときは、たとえ楽譜があったとしても(コード・チェンジを知っているとしても)、最終的には自分(&他のメンバー)のサウンドを耳で聴いてさまざまな判断をすることになります。特にインプロヴィゼイションをする場合は、周囲のサウンドを聴いて反応することが重要です。さらには、実際に音を出さなくても頭の中にサウンドをイメージできるようになれば、アレンジや作曲をする際に強力な武器となります。要するに、さまざまな場面で“このハーモニック・パターンはあれだな!”と即座に耳だけで判断できることは、ミュージシャンにとって強力なアドバンテージとなるんです!
個人的には、ウェイン・ショーター(Wayne Shorter)とかビリー・ストレイホーン(Billy Strayhorn)とか、自分の好きなコンポーザーたちの作品によくある転調の傾向(距離感)やらフローティング感と終止感やら、それらのサウンド的効果を生み出す源となっているであろうファクターを整理して把握できる(そして利用できる)ところが非常に気に入ってます!裏ワザとしては、ソング・フォームとハーモニック・パターンの資料集として、いつでも手に取れるところに置いておくという辞典的使い方も非常にいいと思います。以前ならば、自分で膨大な量の音楽を分析して、自分ならではの方法で整理して、ようやく見えてくるような貴重な情報が山盛りですからね!
そう考えると、この本は便利でありがたい存在です。基礎的なハーモニック・セオリーが理解できているインプロヴァイザー、コンポーザーにおすすめします!
執筆者:佐藤 研司
~佐藤 研司 プロフィール~
リディアン・クロマティック・コンセプト公認講師。
バークリー音楽大学にて、ジョー・ヴィオラ、ジョージ・ガゾーンらに師事した後、
ジョージ・ラッセルのもとに学び、リディアン・クロマティック・コンセプトの公認講師資格を得る。
1998年に帰国以来、さまざまなシーンでパフォーマー、音楽講師として活動中。
トラディションは大事にするが、何でもありの自然派アーティストを目指し、
自作楽器での演奏なども行う。また、ATNの海外教則本、DVDなどの翻訳を担当。